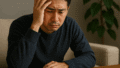「行政書士に合格するのは本当に“すごい”ことなのか?」
近年、行政書士試験の【合格率は6〜15%台】で推移し、毎年約4万人が挑戦しても実際に合格するのは約3,000人前後のみ。その数字が示す通り、合格者は狭き門を突破した証として社会的にも高く評価されています。
一方で「独学でも受かる?」「学歴や年齢は関係あるの?」という口コミや悩みがネット上にはあふれています。SNSや合格者の体験談では、高卒や主婦、異業種からの転身で合格したケースも多数。実際、合格者の約30%以上が法学部以外の出身で、女性比率も年々増加中です。
「今の自分にもできるのだろうか」「本当に価値があるのか」と思い悩む方は少なくありません。しかし行政書士資格は“開業・転職・副業”など幅広いキャリアに直結し、開業後5年以上で年収500万円以上の人も珍しくありません。
迷いや不安を感じている方こそ、「リアルな合格実態」と「実践的な勉強法」「取得後の未来」を知ることで、新たな一歩を踏み出すきっかけになるはずです。
最後まで読んでいただくと、あなたに最適な行政書士合格の道筋と、資格の本当の価値がきっと見えてきます。
行政書士合格は本当に「すごい」のか?世間の評価と資格価値を徹底解剖
行政書士合格の世間的なイメージ・評判
行政書士試験に合格することは世間でどのように評価されているのでしょうか。SNSや知恵袋の声を分析すると、主に以下のような意見が目立ちます。
- 難関資格の象徴
合格率は例年10%前後と低く、「簡単だった」「誰でも受かる」という声もある一方で、現実的にはかなりの努力と勉強時間(600時間~1000時間程度)が必要とされています。そのため、「行政書士に合格するのはすごい」「頭いい」といった称賛の声が多いのが特徴です。
- 信頼とステータス
「行政書士って大学で例えるとどのレベル?」「偏差値は?」といった議論も頻繁ですが、難易度や合格率から見て、法学部出身や難関大学出身者にも高く評価される資格です。大学別の合格率データには偏りがないため、出身大学問わず多様な合格者層が存在します。
- 有益なキャリアの一歩
口コミ・知恵袋では「年収は現実的にどうなの?」「女性や主婦でも独学で合格できる?」といった質問も目立ち、独学合格やキャリアアップを目指す現役世代からの関心も高いです。口コミでは「行政書士は難しいけど合格できて自信がついた」といった前向きな意見が多くみられます。
下記は知恵袋やSNSでよく見られる疑問や感想の一例です。
| 質問・感想例 | 解説 |
|---|---|
| 行政書士に合格するとすごいですか? | 合格率・難易度の高さから、社会的評価が高い資格です。 |
| 行政書士は恥ずかしい資格ですか? | 恥ずかしいという意見は極めて少なく、むしろステータスとする意識が強いです。 |
| 行政書士は誰でも受かる? | 実際は十分な対策がないと合格は難しく、簡単という意見は誤解と言えます。 |
多くの情報源で「行政書士の合格はすごい」と認識されていることが分かります。
行政書士合格者の社会的意義やキャリアへの影響
行政書士に合格することで得られる社会的価値やキャリアへの影響も注目されます。資格取得後の進路は多岐にわたり、幅広い層が活躍しています。
- 独立・開業での活躍
行政書士は独立開業できる国家資格です。自分で事務所を運営し、企業や個人から依頼を受けることで、年収アップも狙えます。実際に年収1000万円を超えるケースも存在し、「行政書士で一番稼げる仕事は?」といった関心も集まっています。
- 活躍の幅広さ
出身大学や学歴に関係なく、高卒や法学部以外の方も合格・活躍しており、大学ランキングから見ても幅広い層がチャレンジ可能です。法学部出身はもちろん、文系理系問わず多数の合格・成功事例があります。
- 女性や主婦のキャリア支援
近年は女性や主婦層の合格者も増加し、実際に「女性の年収実態」や「主婦ブログ」でも話題です。柔軟な働き方ができるのが大きな魅力です。
- 雇われ行政書士の実情や現実的な年収
雇われの場合の年収は約300万円~500万円が多数ですが、スキルや努力次第で独立開業による収入増加も実現可能です。また、行政書士の仕事内容は法律書類の作成や許認可申請など多岐にわたり、社会的責任も非常に大きいものです。
このように、行政書士合格は知識や努力の証明となり、キャリアの幅を広げる大きなチャンスといえます。
行政書士試験の難易度・合格率と偏差値解説
合格率の推移と大学別合格率比較
行政書士試験の合格率は近年おおよそ9%〜12%で推移しています。直近年度でも全国平均合格率はおよそ10%台となっており、決して「誰でも受かる」資格ではありません。難関国立大学や法学部出身が多い一方で、文系・理系や学歴に関係なく社会人や主婦、高卒の合格者も増加しています。特に、上位合格者層にはMARCHや関関同立など偏差値65前後の大学を卒業した受験生が目立ちます。
| 年度 | 総受験者数 | 合格率 | 主な合格者層(例) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 47,870人 | 11.2% | MARCH、地方国立大、社会人 |
| 2023 | 46,253人 | 12.1% | マーチ、法学部以外、主婦・高卒 |
このような合格率から、行政書士は大学一般入試や多くの国家資格と比較しても高い基準を求められる試験です。
行政書士試験の偏差値レベルと具体例
行政書士試験の偏差値は一般的に65程度とされ、MARCHや地方国立大の法学部レベルと同等といわれています。また、出身大学ランキングをみても上位には早慶・MARCHクラスの卒業生が多いものの、専門学校や独学で実力をつける受験生も増えています。下記の表からも偏差値のイメージが明確になります。
| 資格 | 偏差値目安 | 難易度の特徴 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 65前後 | 合格率10%前後、高度な法律知識 |
| 宅建士 | 58~60 | 比較的短期間の学習が主流 |
| 税理士 | 70以上 | 会計系の最難関資格 |
法学や法律知識が未経験でも合格した例が多いですが、科目ごとに基礎から応用力まで幅広く問われるため、十分な学習時間が求められます。独学と通信講座・通学講座の選択も重要です。
他の法律系資格との難易度・合格率比較
行政書士試験と他の主要法律系資格とを比較すると、司法書士や税理士と比べると難易度は一段下がるものの、社会保険労務士や宅建士と並んで国家資格として高い評価を得ています。
| 資格名 | 合格率 | 学習目安時間 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 行政書士 | 約10% | 600~1000時間 | 法律一般、行政法、民法など |
| 司法書士 | 約4% | 3,000時間超 | 不動産・商業登記法など |
| 社労士 | 約7% | 800~1,000時間 | 労働・社会保険法 |
| 税理士 | 約12%(科目合格) | 4,000時間超 | 税法・会計学 |
行政書士試験は数ある国家資格の中でも、独学で合格できる可能性が高い点も魅力です。独立開業や企業内専門職としての需要も高まり、年収やキャリアの幅を広げることにつながります。強い意欲と計画的学習が、高い合格率を突破するカギです。
「誰でも受かる」と「やめとけ」の真実:ネットの声を科学的に検証
短期間合格の現実的な可能性と条件
行政書士試験は「誰でも受かる」「独学で十分」「簡単だった」といった声がネット上でも見られますが、現実には全国平均合格率が約10%前後と、難関国家資格の一つです。合格者の学歴や年齢は幅広く、法学部出身だけでなく高卒や主婦、大学生も多く合格しています。
実際に短期間で合格するには過去問の反復演習、法令科目の重点的対策、スケジュール管理が必須です。独学でも市販のテキストやアプリ、YouTubeの無料講義など多彩な学習方法が選択できます。身近な合格パターンとしては以下のような傾向があります。
| 背景 | 勉強時間目安 | 使用教材例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 高卒・未経験 | 800~1000時間 | テキスト、過去問集、アプリ | 基礎から地道に積み上げる |
| 主婦・社会人 | 600~900時間 | 通信講座、アプリ、スキマ学習 | 時間確保とペース配分が重要 |
| 法学部経験者 | 400~700時間 | 過去問、記述式対策本 | 法令は得意科目にして得点源に |
どんな立場でも自分に適した学習計画を組むことが短期間合格のポイントです。受験資格に制限がないため、努力次第で十分合格可能な試験です。
ネガティブ意見の背景と事実整理
「行政書士はやめとけ」「年収が低い」「独立は無理ゲー」などのネガティブな評判や口コミも珍しくありません。資格取得後の現実には個人差があり、収入や活用の仕方は大きく分かれています。
実際の行政書士の年収は300万~500万円がボリュームゾーンで、開業初年度は低収入になりやすいものの、経験や営業努力によって上昇します。以下の表に平均年収や働き方の違いを整理しました。
| 働き方 | 年収目安 | 主な業務内容 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 事務所勤務 | 300~400万円 | 各種許認可申請補助など | 安定志向、残業少なめ |
| 開業・独立 | 400~800万円 | 独自営業で業務開拓 | 収入差が大きい |
| 法学部卒の進路 | 350~600万円 | 企業法務や行政関連業務 | ダブルライセンス目指す事例も |
「行政書士は頭がいい人向き」といわれる理由は、法律知識・文章力・計画性の3つが求められる点にあります。大学や学歴に依存せず実力勝負となるため、独学や異業種からの合格も多いです。
収入や就職への不安は当然ありますが、活用方法やキャリアビジョン次第で十分に価値ある資格といえます。女性や転職組でも成果を出す方が多数いるため、リアルな年収や仕事内容を事前に把握し、目的に応じた使い方ができるか冷静に見極めることが重要です。
最短合格を実現する究極の学習法と戦略
独学合格者に学ぶ具体的勉強計画と教材選び
行政書士試験に合格するためには、効率の良い勉強計画と適切な教材選びが不可欠です。独学で合格を目指す場合、まず自分に合ったテキストを厳選し、過去問集や問題演習アプリを積極的に活用しましょう。
おすすめの勉強計画としては、以下の3ステップが効果的です。
- 基礎知識の徹底理解(市販のテキスト・講義動画を活用)
- 問題演習による知識のアウトプット(過去問・模試・アプリをフル活用)
- 弱点の発見と反復練習(ノート整理やミス問題の再確認)
教材選びの目安をまとめた表は下記の通りです。
| 分野 | 推奨教材 | 特徴 |
|---|---|---|
| テキスト | 定番市販テキスト 各社 | 基礎から判例、コラムまで網羅 |
| 過去問 | 過去問集+解説書 | 詳細解説で効率的に本試験分析が可能 |
| アプリ | スマホ学習・一問一答アプリ | スキマ時間や反復に効果的 |
独学で合格を目指す主婦や社会人も、動画講義や解説サイトの併用で理解度を高めており、特に「わかりやすい解説」「最新法令対応」という点に注目して教材を選ぶと着実に力がつきます。
予備校・通信講座の賢い活用法と価格比較
効率的な学習環境を求める方は、予備校や通信講座も選択肢となります。各サービスには下記のような特色があります。
| 講座種別 | 強み | 弱み | 価格目安 |
|---|---|---|---|
| 予備校 | 講師の直接指導、対面質問・相談が可能 | 通学の手間、費用高 | 10万~20万 |
| 通信講座 | 自宅で学習完結、繰り返し視聴可能 | 自己管理が必要 | 5万~15万 |
| オンライン | わかりやすい動画・スマホ最適化 | 質問制限の場合あり | 3万~10万 |
多忙な社会人や大学生には通信講座やオンライン学習が適しており、主婦でも家事・育児の合間に受講しやすい点は高評価です。価格やサポート体制を比較検討し、自分に合ったサービスを選びましょう。
効率的な科目別学習法と記述式対策のポイント
行政書士試験で高得点を狙うなら、行政法と民法の攻略がカギです。これらは配点が高く、出題傾向を把握して重点的に対策する必要があります。
-
行政法:判例知識と条文理解を重視。過去問で繰り返し出るテーマに注目
-
民法:具体例と図を用いた理解が有効。論点整理ノートが役立つ
-
憲法・商法:満点を狙わず基本問題を確実に得点
記述式対策は、文章構成・要点の整理力が重要です。頻出テーマをピックアップして、手書きで答案練習を繰り返します。合格者の多くは、過去問題で「なぜこの解答なのか」を掘り下げることで得点アップにつなげています。
このような戦略的アプローチで、最短合格を実現する力を養うことができます。
多様な背景から合格者は生まれる:大学・学歴・性別ごとの合格実態
大学別合格データと偏差値別の傾向分析
行政書士試験の合格者には、有名大学出身者だけでなく、多様な学歴・バックグラウンドの方が含まれています。合格者の出身大学ランキングをみると、上位には東京大学や早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学など高偏差値大学が多い傾向があります。ただし、それだけでなく地方大学や短大卒、高卒の合格者も多数存在し、学歴だけが合否を左右するわけではありません。
下記のテーブルに、大学別と偏差値別にみた主な傾向をまとめます。
| 出身大学 | 偏差値帯 | 合格者数の傾向 |
|---|---|---|
| 早慶上智・国公立 | 65以上 | 比較的多い |
| MARCH | 60前後 | 安定して多い |
| 地方国公立等 | 50-59 | 少なくない |
| 専門・短大 | 45前後 | 毎年一定数 |
| 高卒 | 40前後 | 少ないが毎年合格者あり |
合格者が多い大学は法学部が設置されていることが特徴ですが、非法学部や独学でも合格可能です。行政書士の難易度は確かに高く、一般的には偏差値55~65のレベルですが、地道な努力とバランスのよい学習計画を立てることで、学歴に関わらず合格者が生まれています。
法学部以外・高卒・女性合格者の成功事例
行政書士試験は、法学部以外の出身者や高卒、女性でも十分に合格できる国家資格です。最近の合格者データでも、女性や主婦、社会人でゼロから独学で挑戦し見事合格した人たちが増えています。実際の体験談をみると、「高卒で法律知識ゼロから始めたが、市販の独学テキストと過去問アプリを徹底活用した結果、半年で合格できた」という事例や、「主婦で家事や育児と両立しながら、隙間時間に効率良く勉強し合格した」といった声も目立ちます。
特に女性の場合、「独立・開業で自分らしい働き方を実現したい」「在宅ワークのスキルアップを図りたい」などの理由から、行政書士資格に挑戦する方が多いです。学歴や性別を問わず、戦略的な学習やモチベーションの維持がポイントとなります。
下記リストは、非法学部や高卒、女性の合格実例で多く挙げられる成功要因です。
-
毎日の継続学習と過去問演習に重点を置く
-
市販テキストやアプリなど学習ツールの活用
-
SNSやブログで勉強仲間と情報交換し、励まし合う
-
スキマ時間の有効活用でコツコツ積み上げる
このように、多様な背景から合格者が生まれ、挑戦しやすい資格であることも行政書士ならではの魅力となっています。
資格取得後のキャリア展望と現場での業務内容を詳解
行政書士の主な業務内容と活躍のフィールド
行政書士の仕事は幅広い法律知識を活かし、官公署への書類作成や許認可申請、相続や遺言作成サポートなど多岐にわたります。特に企業法務や建設業、飲食業の許認可、在留資格取得支援、風営法関連業務まで、多様な分野で行政手続きを行うプロフェッショナルです。
近年では、法学部出身者だけでなく、文系理系を問わず様々なバックグラウンドを持つ人が行政書士として活躍しています。
行政手続き以外のフィールドとしては、コンサルティング業務や外国人の在留支援、企業の起業支援や事業承継、会計記帳サービスなども拡大中です。
主な業務フィールドを一覧にまとめました。
| 分野 | 具体的な業務例 |
|---|---|
| 官公署関連 | 各種許認可、届出、建設業許可、風営法、運送業 |
| 相続・遺言 | 遺産分割協議書作成、相続人調査、遺言執行支援 |
| 外国人支援 | ビザ・在留資格申請、永住許可申請 |
| 法人設立 | 会社設立書類作成、各種変更届出 |
| コンサルティング | 経営顧問、事業承継、会計記帳サポート |
行政書士は「独学での合格」「仕事の幅広さ」が注目されており、独立開業志向だけでなく会社員や副業としても活躍できる資格です。
年収構造と独立起業の実態、女性・副業事情
行政書士の年収は働き方や地域によって大きな幅があります。雇われの場合は、年収300万円~500万円程度が一般的ですが、独立すると収入の上限はなく、努力次第で年収1000万以上も目指せます。下記の表で主な年収パターンを比較できます。
| 働き方 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 雇用行政書士 | 300~500万円 | 安定収入、福利厚生有り |
| 独立行政書士 | 500~1500万円 | 実力主義、大きく差が出る |
| 女性のケース | 200~800万円 | 子育て・家庭と両立も可 |
| 副業の場合 | 50~200万円 | 隙間時間に収入プラス |
独立開業するには専門知識だけでなく、顧客を得る営業力やネットワーク作りも必須です。また、女性行政書士や主婦、副業として活躍する方も増えており、特に在宅でできる業務や家事・育児との両立を重視した働き方が可能となっています。
行政書士の資格を取得することで、法律を活かした多角的なキャリア形成や安定した収入・将来の独立も視野に入れることができます。多くの分野でニーズが高まっているため、取得後のキャリアパスや活躍の幅は今後も広がるでしょう。
合格者のリアルな声に基づく勉強法・教材レビューと成功の秘訣
合格者が推奨する教材・アプリの特徴と選び方
行政書士試験に合格した多くの受験生は、効率的に知識を定着させる教材やアプリの選択が成功のカギだったと語っています。実際に合格者の知恵袋や体験談をもとに選定基準をまとめると、次のポイントが注目されています。
| 教材・アプリ名 | 特徴 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| テキスト・参考書 | 図解・要点解説が充実、法改正に対応 | 最新版・条文重視の内容を選ぶ |
| 問題集・過去問集 | 頻出出題の傾向を把握、本試験形式で練習 | 本試験形式で解説が詳しいもの |
| スマホ学習アプリ | 通勤中やスキマ時間にも学習可能 | 解説のわかりやすさを重視 |
特に人気なのは過去問重視型の問題集や、理解を助ける動画講義付きアプリ。また、法学部以外からの合格者も多く、出身大学ランキングや偏差値に影響されにくい点が魅力とされています。「行政書士には誰でも受かる」という見方もある一方で、実際には教材選びと使い方で難易度を乗り越えた声が多数寄せられています。
リストでチェックしたい教材選定のコツ
-
本試験の傾向を押さえた最新版を選ぶ
-
要点・条文・判例がしっかりまとまっている
-
無駄な情報が少ない効率型テキスト
-
スマホやPC対応のアプリでスキマ時間も活用
独学・通学・通信講座別の体験談比較と学習中の注意点
行政書士試験の合格者は独学・通学・通信講座すべての学習方法から生まれています。独学で合格した人は「繰り返し問題集と過去問」に力を入れ、スケジュール管理を徹底していたという声が目立ちます。通信講座の受講者は「講師の動画解説と添削サポート」が精神的な安心感になったという意見が多く、働きながらでも無理なく続けられる点を評価しています。同時に通学講座の経験者は「仲間との情報共有や定期的な模試受験」でやる気を維持したと答えています。
| 学習パターン | メリット | 成功の秘訣 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 独学 | 費用を抑え柔軟に進めやすい | 自己管理と進捗チェック | 孤独感、情報の偏り |
| 通信講座 | 場所時間問わず学習可能 | 添削や質問の活用 | モチベ維持、計画の柔軟性 |
| 通学講座 | 仲間と切磋琢磨しやすい | 模試・勉強会に参加 | 費用負担、通学時間 |
学習を進める上での体験談からは、無理な暗記ではなく、理解重視の学習が合格につながっているとの声が多いです。行政法・民法の基礎知識を体系的に固めることや、過去問でのアウトプット中心の学習法が成功の共通点として挙げられています。独学でも十分に合格可能ですが、市販の独学用テキストやスマートフォン対応のアプリを組み合わせるなど、自己流の工夫が不可欠です。
強調ポイントとして
-
過去問演習を繰り返して出題傾向を把握する
-
分からない部分は積極的に外部サポートを活用する
-
計画的なスケジュール管理が継続の鍵
一人一人の状況やライフスタイルに合わせて、最適な教材や学習スタイルを選ぶことが、行政書士試験合格の近道です。
よくある疑問と誤解の徹底解消Q&A
試験・資格に関する質問と回答
Q1. 行政書士試験の難易度はどの程度ですか?
行政書士試験は毎年合格率が約10%前後に留まる国家資格で、誰でも受験可能ですが、その分十分な知識と対策が必要です。特に行政法・民法が高い出題割合を占めており、合格するためには法令科目と一般知識で基準点を満たし、総合得点で合格ラインに達することが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 合格率 | 約10%(近年実績) |
| 合格基準 | 法令等:244点以上、一般知識:24点以上、総計:300点/600点以上 |
| 難易度比較 | 法学部偏差値で例えるとMARCHレベル |
Q2. 独学合格は可能ですか?
独学でも十分に合格は可能です。分かりやすいテキストやアプリ、過去問演習を活用し、600〜1000時間程度の学習時間を目安としてください。実際に主婦や高卒からでも独学で合格した例は数多くあります。自分に合った教材選びやスケジュール管理が重要です。
-おすすめの独学ツール-
- テキスト(通学不要・効率学習)
- 過去問集(傾向分析用)
- スマホアプリ(スキマ時間に反復)
Q3. 大学名や学歴は合否に影響しますか?
行政書士試験は年齢や学歴不問で受験できます。大学や出身学部、偏差値に関係なく合格できます。近年では法学部以外や高卒、専門学校卒業者も多く合格しており、努力次第で誰にでも合格のチャンスがあるのが特徴です。
資格活用や将来設計に関する質問と回答
Q1. 行政書士の取得で年収はどのくらい変わりますか?
行政書士の平均年収は300万~600万円程度ですが、独立・開業や事務所勤務、雇われなど働き方で大きく異なります。特に得意分野を持ち、多様な業務を受任することで収入アップが見込めます。女性や若手でも実績を重ねれば着実に高収入を目指せる資格です。
| 働き方 | 年収目安 |
|---|---|
| 雇われ | 300万〜400万円台 |
| 独立開業 | 500万円〜1000万円以上も可 |
-収入アップのポイント-
-
法務書類や許認可申請、建設業・法人設立業務など高需要分野に挑戦
-
他士業との連携やネット集客の活用
-
継続的な営業努力と専門性磨き
Q2. 独立開業の現実と成功のコツは?
独立は簡単ではありませんが、継続的な学びと集客、口コミや信頼獲得が成功のカギです。資格取得直後からすぐに高収入を得られるわけではありませんが、地道な業務経験やネットワーク拡大で差が出ます。行政書士として安定したキャリアを築く方も多いです。
-独立後の成功事例-
- 建設業許可申請などの専門特化
- SNSやウェブサイトでの情報発信
- 資格取得後の継続学習・自己研鑽
Q3. 行政書士は他の資格と比較して頭が良くないと合格できませんか?
行政書士は大学受験の偏差値で例えると中堅大学レベルの知識が求められますが、「頭の良さよりも継続的な努力・独自の勉強法が重要」です。実務知識や経験が問われるため、早めの学習計画・過去問トレーニングで合格可能性を高めましょう。
-おすすめの勉強法-
-
基礎知識のインプット→問題演習→弱点補強のサイクル
-
法律初学者は要点整理や用語確認から始める
-
記述式対策には文章構成力の訓練も有効
よくある疑問を理解し、合格に向けて前向きに学習を続けることが重要です。資格取得後の活躍も視野に入れ、計画的に行動を起こしましょう。
最新統計データと信頼できる情報源の活用で徹底的に信頼性担保
公式データの見方と活用法
行政書士試験の最新合格率や資格の難易度は、法務省や各試験実施機関が公表する統計データが信頼できる基準です。合格率は例年約10%前後とされ、特に年度ごとの推移や法令科目の出題数に注目することで、対策すべきポイントが明確になります。大学別の合格率や出身大学ランキングにも公式データが使われており、科目別・大学別の分析によりそれぞれの特徴や傾向を確認することが可能です。更新は毎年行われるため、過去5年の動向を比較し、難易度や試験内容の変動を把握しましょう。
下記のポイントを押さえて情報収集を行うことが重要です。
-
毎年公式機関が発表する合格率やデータを参照する
-
合格率だけでなく科目別の得点配分・傾向も比較
-
推移や変動をチェックし難易度の変化を掴む
これらの公式データ活用により、曖昧な情報や知恵袋などの噂話に惑わされず、信頼度の高い情報に基づいた戦略的な学習が可能になります。
競合との差別化となる独自調査や分析
独自のアンケートや利用者の声を集計し分析することで、受験者の実体験や合格者の特徴など公式データだけでは見えない具体的な情報を網羅できます。たとえば、主婦や大学生、高卒の独学合格者の学習法や、実際に使われている独学テキスト・アプリ、おすすめ通信講座の活用法についても詳細なリサーチが進められています。
近年増えている独学での合格者に注目し、人気テキストや勉強法の傾向も独自調査でまとめました。
| 合格者層 | 主な学習スタイル | おすすめ教材例 | 合格までの平均勉強時間 |
|---|---|---|---|
| 大学生 | 通学・独学 | 基礎系テキスト | 約800~1000時間 |
| 社会人 | 通信・独学 | 過去問アプリ | 約900時間 |
| 主婦 | 独学・通信 | 通信講座セット | 約1000時間 |
独自アンケートの結果によると、行政書士試験は「誰でも受かる」とは言い難く、効率よく継続的な学習を行った方ほど合格率が高い傾向です。また、資格取得後の年収や仕事内容に対するリアルな声もヒアリングし、「年収が低い?」という疑問や「女性でもキャリアアップができるか?」などの切実な不安にも具体的な事例を用いて解説しています。これらの情報を一元的に把握することで、他の情報源との差別化と信頼性向上を実現しています。