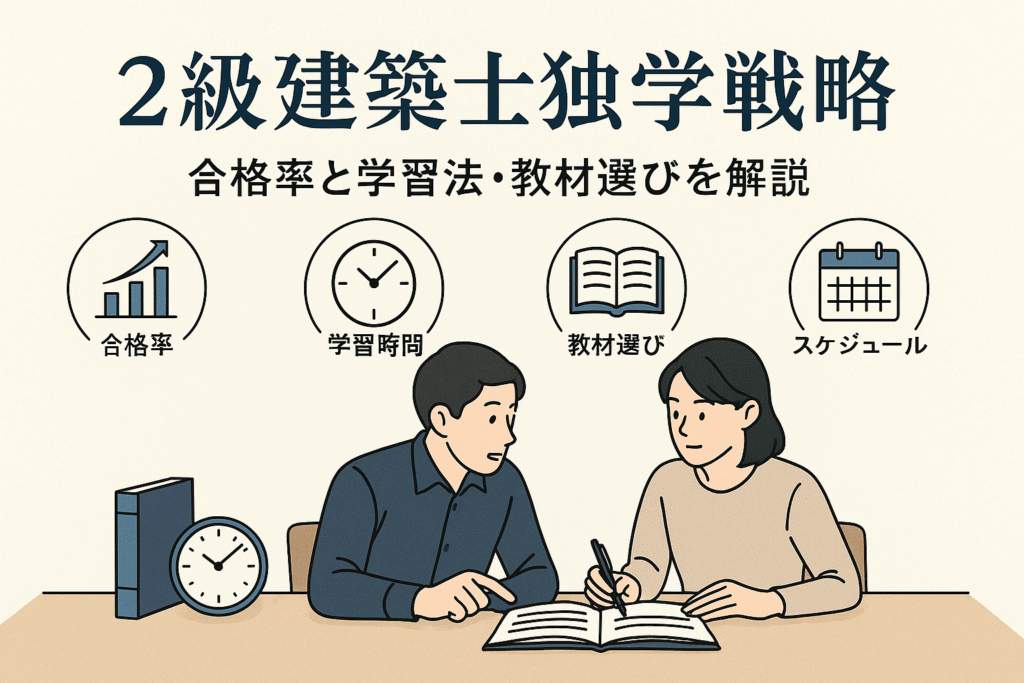「2級建築士を独学で目指したいけれど、本当に合格できるのか不安…」「仕事や家庭との両立で毎日どこまで勉強すべき?」そんな悩みはありませんか?
実際、2級建築士試験の学科・製図をあわせた全国平均合格率は【約22%】。独学で挑戦する人の割合は年々増加し、近年は受験者全体の【およそ4割】が独学にチャレンジしているという最新データも出ています。一方で「過去20年分の過去問演習が合格の鍵」と言われる通り、正しい教材選びと効率的な学習計画が成否を大きく分けます。
独学は「自由度が高い反面、情報の取捨やスケジューリングの難しさ、孤独からのモチベーション低下に直面しやすい」ことも事実。それでも、社会人や主婦などさまざまな方が「平均700時間前後」の学習を積み重ねて合格を手にしています。
このページでは「独学に必要なリアルな勉強時間の目安」「最新人気テキスト&アプリの選び方」「心理的な挫折ポイントと実践的な克服術」を、実際の合格者データと現場知見に基づいて徹底解説。
「失敗したくない」「最短で合格したい」あなたへ――読み進めれば、今からでも独学合格が現実になるロードマップと対策法が手に入ります。
2級建築士は独学の現実と成功可能性を見極める – 独学者の特徴と心得
2級建築士試験は独学合格も十分可能ですが、事前の現実的な理解が合否を左右します。専門学校や通信講座と比較し「独学は本当に無理ではないのか?」と不安を抱える方が多いのも事実です。下記のような特徴が独学合格者には見られます。
-
明確な学習目標を持ち、長期的な計画を自分で立てられる
-
自己管理能力が高く、勉強の進捗を可視化して修正できる
-
わからない点を能動的に調べる習慣がある
試験の難易度や出題傾向を把握しつつ、最新の教材や過去問で学び続ける姿勢が求められます。途中で挫折しやすい独学スタイルでは、モチベーション維持のためにSNSや勉強アプリ、ブログなどで情報共有を活用している人も増えています。
二級建築士独学合格率の最新データ分析
二級建築士試験の合格率は毎年20%〜25%前後で推移しています。独学者の正式な割合は非公開ですが、受験生全体のうち独学合格者は30〜40%と言われています。
年度別合格率の推移
| 年度 | 学科合格率 | 製図合格率 | 総合合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21.7% | 46.0% | 約22% |
| 2022 | 23.1% | 44.5% | 約23% |
独学合格を目指す場合、700時間前後の学習時間の確保がひとつの目安です。過去問分析や複数年度分の問題演習は合格に不可欠です。
独学が難しいと言われる具体的要因と克服法
二級建築士の独学が難しい主な要因は、特に製図試験の実技と学習の継続性です。下記によくある課題と克服ポイントをまとめます。
独学が難しい理由:
-
製図試験の添削やフィードバックが得られない
-
短期間(3ヶ月など)の詰め込み独学は理解不足を招く
-
モチベーションの維持が自己責任になりやすい
-
疑問点の解消や最新法改正情報のフォローが困難
克服のための具体策:
-
オンライン添削サービスや独学者向けコミュニティの活用
-
公式テキストやおすすめ過去問アプリで反復演習
-
学習進捗アプリ・日々の勉強記録で自己管理の徹底
-
法令集・製図テキストは最新版を必ず入手し確認
製図対策では、自己添削ノウハウやYouTubeの解説動画を併用している受験者も増加中です。
独学に向く人・向かない人の見極めポイント
独学の向き不向きは下記の観点から判断できます。
| チェックポイント | 独学に向く人 | 独学に向かない人 |
|---|---|---|
| 学習時間の確保力 | 週15時間以上を継続できる | まとまった時間が取れない |
| 自己管理能力 | 計画・記録が得意 | スケジュールが苦手 |
| 建築基礎知識 | 既にある・実務経験あり | 初心者・ゼロから |
| 疑問点の解決手段 | 調べて解決が得意 | 人への質問が必要 |
向いている方の特徴として
-
強い自己主導力
-
客観的な自己評価ができる
-
ネット教材やアプリの活用が得意
向いていない方は通信講座や講習利用も検討することが合理的です。スケジュールの管理や専門的な添削が必要な場合は独学だけにこだわらず、最善の学習スタイルを選びましょう。
2級建築士試験の基礎知識と独学で押さえるべき試験構造
二級建築士試験の構成と特徴の全解説
二級建築士試験は「学科試験」と「設計製図試験」に分かれています。学科試験は「計画」「法規」「構造」「施工」「環境設備」といった5科目で構成され、マークシート形式で実施されます。各科目ごとに合格基準点が設定され、合計得点と科目ごとの得点で基準を満たす必要があります。
製図試験は手書きでの図面作成が求められ、課題ごとに求められる内容が異なります。設計条件や図面の正確性が評価のポイントです。各試験の試験時間や合格基準は下記の通りです。
| 試験区分 | 内容 | 試験時間 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 学科試験 | 計画、法規、構造、施工、環境設備 | 7時間20分 | 総得点の60%以上 各科目30%以上 |
| 設計製図試験 | 図面作成(課題に沿った住宅設計など) | 5時間 | 減点方式で基準以下は不合格 |
初学者には学科試験の範囲や製図試験課題の出題傾向を事前に把握し、独学でも効率良く対策できるよう準備することが大切です。
受験資格・申込手続きの詳細解説
二級建築士の受験資格は学歴・実務経験によって細かく規定されています。一般的には下表のいずれかを満たせば受験が可能です。
| 学歴・資格 | 実務経験要件 |
|---|---|
| 指定大学卒業 | 不要 |
| 短大・高専卒業(建築学科) | 不要 |
| 高校卒業(建築系) | 3年以上 |
| 高校卒業(非建築系)、他資格保有 | 4年以上 |
申込は毎年春から初夏(例:2025年は4月~5月)にかけて受付。インターネットまたは郵送で手続きします。必要書類としては卒業証明書や実務証明書、写真などが求められ、期日までに用意する必要があります。募集要項の確認と、早めの準備がスムーズな受験のポイントとなります。
独学に必須の試験範囲と重点ポイントの整理
効率良く合格を目指すには、出題が多い分野や過去問で繰り返される内容に重点を置きましょう。
-
過去20年分の過去問を中心にした学習
-
「法規」「構造」は配点が高く、頻出テーマ
-
学科は「施工」「計画」「環境設備」もバランスよく
独学の場合は、市販のテキストやおすすめ参考書、解説が分かりやすい問題集を活用し、学習サイトや過去問アプリも取り入れると効率アップが狙えます。製図対策は、出題経験の多い課題を実際に描いてみることで本番力が身につきます。下記のような優先順位で勉強しましょう。
- 法令集・法規分野の徹底理解
- 構造の基本問題・計算スキル養成
- 各科目の頻出テーマをテキスト・問題集で復習
- 製図課題は自分で手を動かし図面作成を反復
効率と得点力アップのためには、各分野の出題傾向を必ず分析し、無駄なく対策を進めることが重要です。
独学者が設計するべき学習時間・スケジュール戦略:期間別計画と日常活用術
合格に必要な総学習時間と平均時間の根拠解説
2級建築士試験の合格を目指す際、独学での総学習時間は約600〜700時間が目安とされています。初心者や社会人の場合、この数字を基準に学科と製図でバランス良く配分することが重要です。一般的なおすすめ配分は以下の通りです。
| 区分 | 学習時間目安 |
|---|---|
| 学科 | 400〜450時間 |
| 製図 | 200〜250時間 |
忙しい社会人や家庭と両立したい方は、1日2~3時間の学習を積み重ねるのが現実的です。例えば学科は過去問や一問一答形式で毎日短時間でも継続し、製図対策は週末や休日にまとまった時間を設けて集中すると効率的です。これにより得点アップや合格率向上を目指せます。
年間・半年・3ヶ月・1ヶ月プランの具体的スケジュール例
学習期間ごとに最適なスケジュールを立てていくことが合格への近道です。
| 期間 | 毎日の学習時間 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1年 | 2時間 | 基礎知識定着+過去問反復 |
| 半年 | 3~4時間 | 応用問題+模試演習 |
| 3ヶ月 | 5~6時間 | 弱点補強+総仕上げ |
| 1ヶ月 | 6~8時間 | 直前対策+製図演習 |
時間が限られている場合は、【1】平日:通勤・スキマ時間に学科の暗記やアプリ活用、【2】休日:3時間以上まとめて製図練習、というメリハリ型スケジューリングがおすすめです。特に短期で合格を目指す場合、直近10年分の過去問を絞って効率良く反復することで、知識の定着と傾向把握が可能となります。
生活スタイル別おすすめ時間管理法と継続のコツ
独学での合格には自分に合った時間管理と継続の工夫が欠かせません。以下に生活スタイルごとのコツをまとめます。
-
仕事が忙しい方:朝の30分+夜1時間を習慣化し、通勤時間は問題集やオンライン講義で有効活用。
-
家庭と両立する方:家族と協力し、週1回の学習デーを設ける。お子様が寝た後や早朝もおすすめ。
-
モチベーション維持:進捗を見える化するスタディプランナーを使用する。週末ごとに自分を小さくご褒美。
気分転換法としては、学習環境を変えたりカフェや図書館を活用したりすることも効果的です。集中力が切れた場合は、5分間のストレッチや軽い散歩でリフレッシュし、効率良く知識を定着させることを心がけましょう。
失敗しない2級建築士独学テキスト・問題集・教材選び – 質と実用性の徹底比較
市販テキスト・問題集の最新人気ランキング
2級建築士の独学には、実績と分かりやすさを兼ね備えたテキスト・問題集の選定が不可欠です。近年の受験者に特に支持されている主な教材を比較し、特長を分かりやすくまとめました。
| タイトル | 特徴 | 対応分野 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| わかって受かる2級建築士シリーズ | 図解が豊富で初学者向き、重要ポイントが明確 | 学科・製図 | ★★★★★ |
| 日建学院公式テキスト | 最新の法令・出題傾向完全対応、実績抜群 | 学科・製図 | ★★★★☆ |
| 総合資格学院 教材セット | 受験生の多くが使用、演習問題が充実 | 学科 | ★★★★☆ |
| 2級建築士 過去問題集 | 20年分の過去問、詳細な解説付き | 学科 | ★★★★★ |
| 建築士テキストランキング上位書籍 | 口コミ評価・売上ともに上位を維持 | 学科 | ★★★★☆ |
ポイント
-
初心者には図やイラストが豊富な解説書、受験経験者には過去問集や一問一答集を推奨
-
最新版かつ法令改正に対応した教材を選ぶことが重要
過去問活用法と一問一答、アプリ無料教材のベストプラクティス
2級建築士試験で高得点を狙うには、過去問・一問一答形式、そしてデジタル教材を組み合わせるのが効果的です。効率を最大化するステップを紹介します。
過去問活用のコツ
- 20年分の過去問を繰り返し解いて出題傾向を把握
- 分野別問題集で苦手分野をチェック
- 一問一答アプリでスキマ時間を活用し暗記強化
- PDFやWEBの問題サイトを活用し、無料教材も有効利用
人気の無料アプリ例
-
2級建築士過去問アプリ(分野・年度別出題対応)
-
一問一答特化アプリ(暗記・復習機能搭載)
ポイント
-
再検索ワードで人気の「過去 問 アプリ」「問題サイト」「PDF」は繰り返し利用して知識定着
-
誤答や苦手問題の記録・分析をすると理解が深まる
製図用教材・道具・法令集の選び方徹底ガイド
2級建築士の製図対策には、最適な教材と使いやすい道具の選定、使える法令集の用意が合格のカギとなります。
製図教材・道具の選び方リスト
-
製図初心者には「丁寧なプロセス解説書」がおすすめ
-
製図道具は、描きやすさ・疲れにくさ重視の製図ペンや定規を選択
-
レビューやランキング上位の「製図セット」は信頼性が高い
-
法令集は、条文の見出しつき・インデックス加工が施された最新版を選択
購入先一例
| 分野 | おすすめ教材/道具 | 主な購入先 |
|---|---|---|
| 製図テキスト | わかって受かる建築士 製図 | 書店、通販 |
| 製図道具セット | 製図専用セット(ステッドラー等) | 画材店、通販 |
| 法令集 | 2級建築士 法令集(最新版) | 書店、専門サイト |
選び方のポイント
-
製図講座用として市販・学校推奨教材を事前リサーチ
-
法規対策は索引しやすい法令集、製図は練習用課題付き教材を優先
-
独学者向けサポート付きWEB教材や無料解説も積極活用
これらのポイントを押さえて質と実用性を重視した教材選びが、独学合格の最短ルートです。
実践!2級建築士独学勉強法と集中力維持テクニックの全て
合格者の勉強スケジュール例と日々のルーティン
2級建築士を独学で合格した多くの受験者は、学科と製図の両方を意識した学習スケジュールを徹底しています。特に学科試験対策では、法規・構造・計画・施工の4科目ごとに重点を置いて時間を配分し、製図試験対策では毎週実際に図面を描き続けることが大切です。
下記は参考になるタイムスケジュールの一例です。
| 勉強期間 | 学科対策(時間/週) | 製図対策(時間/週) | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1〜6ヶ月 | 12〜15時間 | 2時間 | 基本知識の習得と過去問反復 |
| 7〜9ヶ月 | 8時間 | 6時間 | 弱点補強・製図練習開始 |
| 10〜12ヶ月 | 4時間 | 12〜14時間 | 製図に特化・模試活用 |
効率的な日々のルーティン例
- 朝、30分ほど法令集や一問一答アプリで知識をインプット
- 夜に過去問を解き直し、誤答をノートに整理
- 週末は模試を実施し、本番を想定した時間管理を意識する
合格への近道は地道な継続です。指導校の模試や無料アプリも積極的に活用しましょう。
苦手科目対策・法規や製図の攻略ポイント解説
2級建築士の独学では、法規と製図でのつまずきが多い傾向にあります。法規分野は、条文の暗記よりも「法令集を素早く引けるスキル」が重要です。勉強法のコツは、過去問ごとに根拠となる条文を自身の法令集にマークし、繰り返し引き直して記憶を定着させることです。
製図対策では、図面を描く手順を徹底的にルーティン化します。まずは簡単な平面図から始めて、徐々に断面図・立面図へと難易度を上げましょう。添削サービスの利用や、合格者が投稿している独学ブログの情報も有益です。
効率的な知識吸収テクニックとしては
-
出題頻度が高いテーマを優先
-
動画解説やアプリを活用して理解の定着
-
間違えた範囲は「なぜ間違えたか」を自己分析
この積み重ねが、合格をグッと現実的に近づけます。
モチベーション維持と疲労対策の科学的手法
独学で長期間の試験勉強を続けるには、集中力とメンタル維持がポイントです。まず学習時間の区切りを「ポモドーロ・テクニック」(25分勉強+5分休憩)としてリズム化することで、脳の疲労を最小限に抑えられます。
人間心理を利用したコツとしては、進捗が見える可視化ツールを活用することが効果的です。学習の記録を残すことで「昨日より前進した」と実感しやすく、自己効力感が高まります。
疲労回復には
-
ストレッチや軽い運動
-
一日に一度は外へ出る習慣
-
睡眠の質を高める意識
を持つことが推奨されます。学習サイトやSNSの合格体験談からも刺激を受け、孤独感をなくしながら挑戦しましょう。
独学者が無料で使える教材・コミュニティ・ネットワークの活用術
無料過去問サイト・PDFなど信頼できる無料教材の紹介
2級建築士独学には公式過去問や模範解答、法令集PDFを効率よく活用することがポイントです。無料で利用できる主要な教材は次のとおりです。
| 種類 | 主な入手先 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 過去問PDF | 公的機関・資格団体HP | 出題傾向や難易度把握、演習・復習に最適 |
| 法令集PDF | 建築関連HP | 法規対策の必須アイテム。条文ごとの検索も可能 |
| 模範解答 | 試験主催者HP | 自己採点や復習に使い、理解不足箇所を確認できる |
ステップバイステップ活用法
- まず公式の過去問PDFで実践演習を繰り返す
- 解けなかった問題は模範解答で根拠まで解説確認
- 法令集PDFで法規の条文を調べ、必ず自分なりにノートへまとめる
無料教材を繰り返し活用することで、合格に必要な知識と実践力が着実に身につきます。
人気のYouTube講座や勉強サポートアプリの選び方と活用例
動画解説や勉強アプリは独学者にとって現代の強力な学習サポートです。講座ごとに特徴が異なるため、自分に合ったものを選びましょう。
-
YouTube講座の特徴
- 無料で学科・製図の基礎~応用まで解説
- 質問コーナーやライブ配信でリアルタイムに疑問解決
- 反復視聴しやすく要点の復習が効率的
-
勉強アプリの例
- 過去問一問一答アプリ:スキマ時間に効率良く学科対策
- クイズ型法令集アプリ:繰り返し練習で暗記力が安定
- スケジュール管理アプリ:毎日の目標を可視化し自動リマインダーで進捗管理
SNSやフォーラムでおすすめ教材の情報交換を行い、不明点は動画やアプリの無料解説で補うのが現代的な独学スタイルです。
オンライン・オフライン学習コミュニティの参加ガイド
学習の継続やモチベーション維持には、コミュニティの活用が不可欠です。
-
オンラインコミュニティ
- 建築士専用フォーラムやSNSグループは質問・情報交換に最適
- 合格者の経験談や学習スケジュール例が共有されている
- 勉強会の案内、模擬試験の共有もあり有益
-
オフラインの勉強会
- 地域のリアル勉強会や自習会は仲間と刺激し合いながら成長可能
- 集合知を活かした課題のグループ討議に役立つ
コミュニティ参加時のポイント
-
自分からも積極的に質問・情報発信することで参加価値が高まる
-
合格者のアドバイスや模擬試験情報を能動的に取り入れる
-
時間が合わない場合は、録画や掲示板を活用し自分のペースで学習できる
コミュニティの力を借りれば、独学でも孤独感を乗り越え、必要な知識や最新情報を効率良く吸収できます。
独学と通信講座・通学講座のメリット・デメリット徹底比較
独学・通信講座・通学講座の特徴と向き不向き分析
2級建築士試験の学習方法には独学、通信講座、通学講座の3つがあります。それぞれに特徴があり、選び方で効率や合格率が変わります。
独学は自分のペースで進められ、費用を大きく抑えられる点が魅力です。しかし、スケジュール管理や疑問点の解決に自信のない方は負担が大きくなりがちです。通信講座はプロのノウハウや添削体制が整っており、仕事や家庭と両立したい社会人におすすめです。通学講座は講師や仲間と直接交流でき、強制力があるので、モチベーション維持が苦手な方や早期合格を目指す学生に最適です。
-
学習効率重視なら通信・通学講座が有利
-
費用を抑えたい方には独学
-
社会人は通信講座、学生は通学講座もおすすめ
主な通信講座・専門学校の内容・価格・サービス比較(表案)
通信講座・専門学校を価格・教材・サポート体制で比較しました。受講判断や乗り換え時の参考にご活用ください。
| 講座・学校名 | 費用(税込) | 主教材 | サポート体制 | 合格実績・特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ユーキャン | 約92,000円 | フルカラーテキスト、過去問題 | 添削10回・質問無制限・Web動画 | 初心者向け。手厚いサポートで安心感重視 |
| 総合資格学院 | 約320,000円~ | 独自テキスト、製図教材 | 個別添削・質問フォロー・通学併用可 | 高合格率。直前対策や本番形式講義が充実 |
| 日建学院 | 約280,000円~ | 独自テキスト、法令集 | 個別指導・ライブ授業映像視聴 | 実績多数。学科・製図両対応、アクセス性良好 |
| TAC建築士講座 | 約120,000円~ | オリジナル教材・Web講義 | 質問サポート・添削指導 | 理論重視。短期間で効率良く知識習得が可能 |
選ぶ際のポイント
-
費用とサポート内容を照らし合わせて最適解を判断
-
教材内容や合格実績も重要な選定基準
独学で挫折した場合の乗り換えタイミングと対策
独学で思うように進まない場合、早めの見直しが重要です。下記の症状が見られたら通信講座等への切り替えを検討しましょう。
挫折のサイン
-
勉強スケジュールが大幅に遅れる
-
過去問や模試の点数が伸びない
-
一人での勉強に限界を感じる
効果的な対策と乗り換え方法
- 状況把握
進捗や弱点を客観的に分析し、学習記録をまとめる - 無料相談や体験講座の活用
各社の資料請求や体験授業で自分に合う講座を見極める - 切り替え時期は早めに
モチベーションが完全に下がり切る前に新しい学習法を導入する
スムーズな乗り換えのコツ
-
これまで使用した参考書やノートも並行活用することで無駄を減らす
-
質問サポートや添削指導を積極的に活用し弱点を即解消する
最適な学習法を柔軟に取り入れることで、2級建築士試験の合格可能性を大きく高められます。
二級建築士試験独学に関するよくある質問集(Q&A形式で7~10項目内包)
合格率はどのくらい?独学でも可能?
二級建築士試験の合格率は例年20~25%前後で推移しています。独学で合格することは十分可能ですが、継続力や計画的な勉強が不可欠です。特に初学者の場合は効率のよい学習スケジュールを立て、過去問演習を重視することが成功のカギです。独学合格者も多く存在し、正しい方法と自己管理ができれば十分に実現可能です。
どれくらいの勉強時間で合格できるか?
独学の場合、合格までの目安は約700時間とされています。これは社会人が仕事と両立しながら1日2~3時間の学習を半年から1年かけて行うイメージです。勉強時間の目標はライフスタイルに合わせて設定し、無理のない範囲で日々の学習を続けることが大切です。計画段階で週ごと、月ごとの進捗も管理しましょう。
仕事しながら独学は無理?
社会人が仕事と勉強を両立させるのはたしかに簡単ではありませんが、しっかりしたスケジュールと学習の習慣化で十分可能です。時間を細かく区切って学習スケジュールを組むこと、移動中やスキマ時間にアプリや過去問解説を活用することがポイントです。また、疲労が溜まった日は思い切って休むなど、自己管理も重要です。
製図試験の独学対策ポイントは?
製図試験の独学は特に対策が重要です。過去問を繰り返し描いて手を慣らすこと、作図スピードの向上を意識するなど日々の練習が合格への近道です。また、作図ミスの傾向を自己分析し、添削機会が少ない独学でも合格者の図面や解説付き教材を参考に設計意図までしっかり理解しましょう。最新の出題傾向も常に確認してください。
テキストや問題集は何を使うべきか?
教材選びは効率的な学習に直結します。おすすめの市販テキストは、法令集や過去問題集と、分かりやすい参考書を組み合わせて利用することです。下記のような教材が人気です。
| 分野 | おすすめ教材名(例) | 特徴 |
|---|---|---|
| 学科対策 | 「総合資格 学科テキスト」「日建学院 テキスト」 | 基礎から重要ポイントまで網羅 |
| 製図対策 | 「製図試験問題と解説」 | 図面例や減点ポイントが分かる |
| 法令集 | 「総合資格 法令集」「TAC 法令集」 | 必須条文が見やすく検索性が高い |
独学の方は理解しやすさ・解説の丁寧さ・最新の出題対応かを基準に選ぶと安心です。
過去問は何年分やれば良いか?
理想的には直近10年分の過去問を複数回繰り返すのが効果的です。過去問演習を通じて出題傾向やよく出る論点を把握し、苦手分野にも気づきやすくなります。新しい年度の問題ほど最新の出題形式に合わせているので、優先して取り組みましょう。復習時は正答だけでなく、間違えた理由も振り返ることが大切です。
モチベーションの維持方法は?
長期間の独学はモチベ維持が鍵です。以下の工夫が効果的です。
-
週間・月間目標を紙に書き出して可視化
-
合格後の自分をイメージし、定期的に振り返る
-
SNSや独学仲間との情報交換で刺激を受ける
-
休息日も計画し燃え尽きを防ぐ
このような工夫で日々の積み重ねがしやすくなります。
無料教材と有料教材はどう使い分けるか?
無料教材は基礎知識のインプットやスキマ時間の復習に有効です。例えばインターネット上の解説サイトや過去問アプリなどが活用できます。一方で有料教材は体系的な学習や最新傾向の把握、分かりやすさの点でメリットが大きいです。基礎は無料で固めつつ、苦手分野や得点源にしたい部分は有料教材を併用すると効率的です。
独学中の失敗例と回避策は?
独学で多い失敗例は「計画倒れ」「理解不足のまま進める」「情報の鵜呑み」などです。対策としては次のような方法が効果的です。
-
週ごとに目標を設定し進捗チェックを習慣化
-
分からない点は複数の資料や公式発表で確認
-
SNSやブログなど信頼できる情報源を選び、噂話に惑わされない
-
本試験を意識して時間管理練習や模試を実施
計画的にコツコツ進め、焦らず確実に知識を習得していきましょう。